単元の流れ
この単元では、双括型の文章の構成や要旨に焦点を当てて指導していく。
- 1時間目文章の構成をまとめる
- 2時間目要旨を捉える
- 3時間目音読・段落分け
◎「具体例はいくつある?」
- 4時間目「初め」「中」「終わり」に分ける
◎「具体例はどこから」 ◯「筆者の主張はどこ」
- 5時間目「中」を分ける
◎「『中』を二つに分けるならどこ?」
- 6時間目原因と結果を使って、自分の考えを伝える
(情報:「関係をとらえよう 原因と結果」)
- 7時間目文章の要旨を捉える
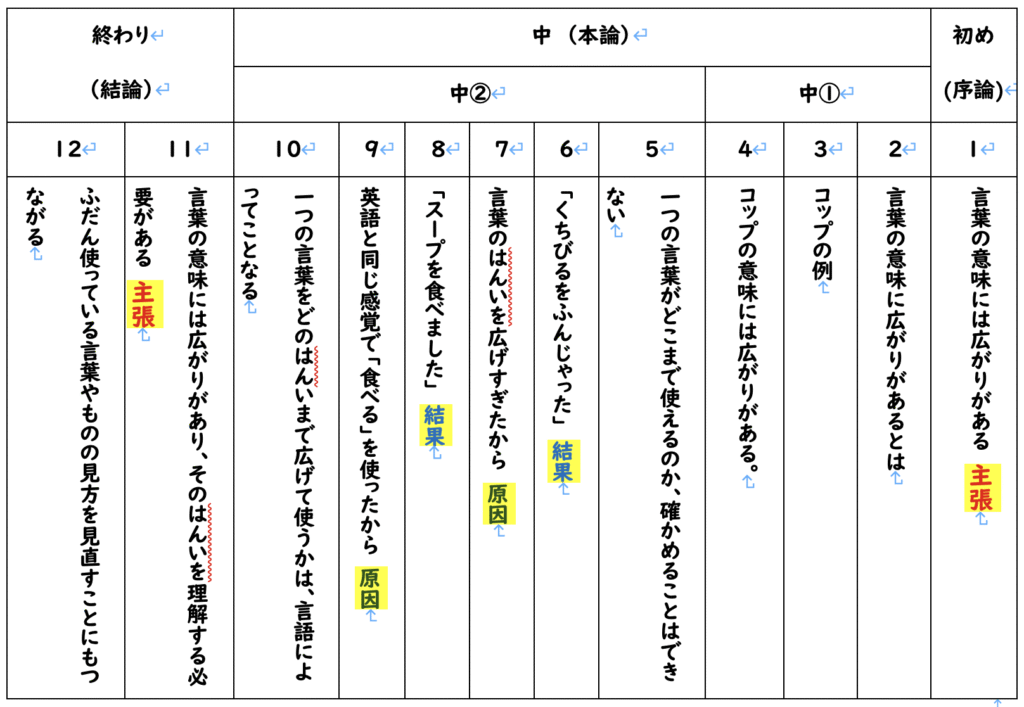
7時間扱い。「見立てる」の説明文で、文章の構成と要旨の捉え方を学習し、「言葉の意味が分かること」の学習に活かす。
3時間目
- 10分教師の範読
段落分け:12段落
- 15分具体例を見つける
◎「具体例はいくつある?」
「コップ」「くちびる」「スープ」の3つ
- 20分段落③〜⑨の要点をメモする
文章の構成図(ワークシート)に要点をメモする
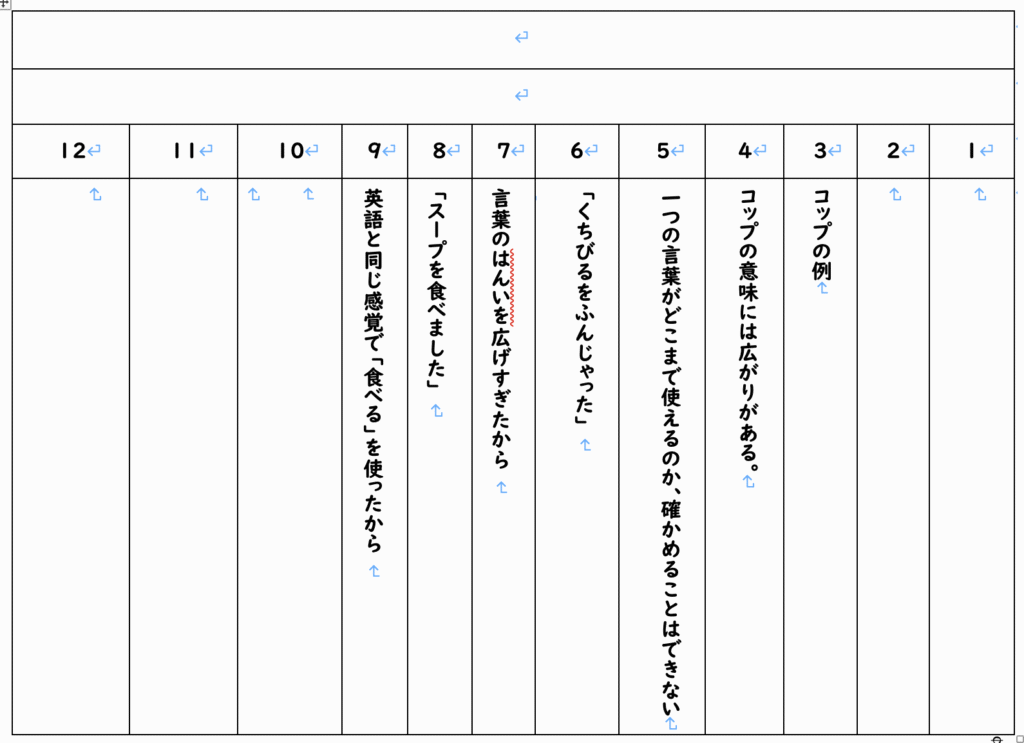
「具体例」を見つける
「初め」「中」「終わり」に分けるためには、「中」の具体例を見つけることで分けやすくなる。
この説明文の学習の最初の時間なので、学習することを伝える。(①「筆者の主張を探して、要旨をまとめること。②「見立てる」と違い文章が長いので、「中」も分解しながら読んでいくこと。)
4時間目
- 5分音読練習
(「中はどこからか」考えながら音読)
- 30分「初め」「中」「終わり」に分ける
◎「具体例はどこから」
◯「筆者の主張はどこ」→「初め」「終わり」にある(双括型)
- 10分残りの段落の要点をメモする
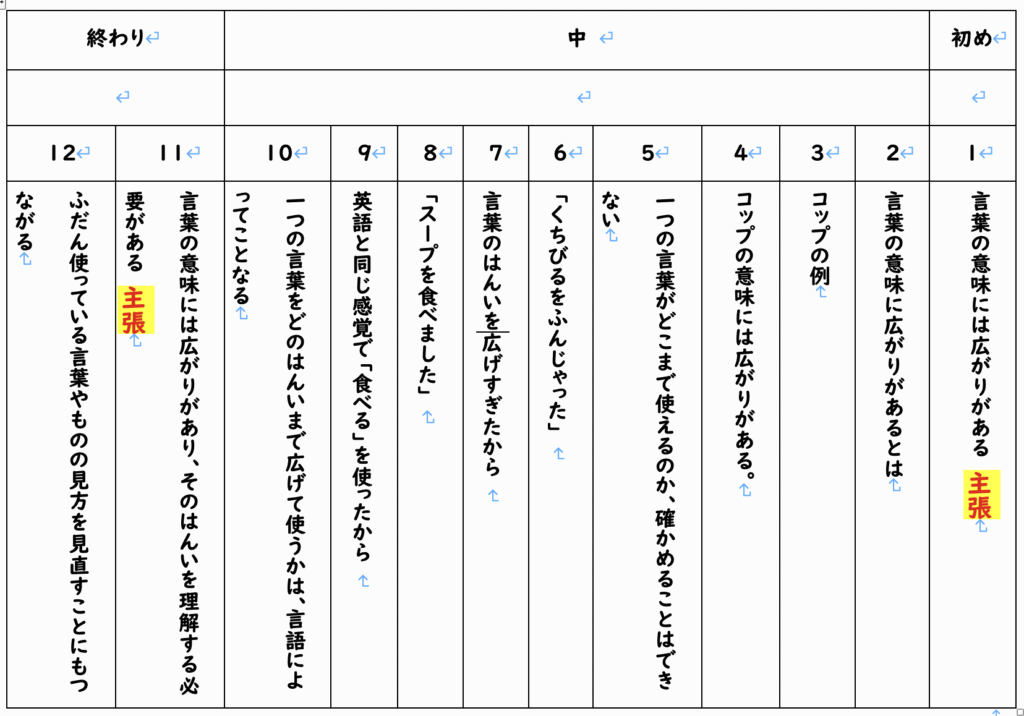
◎「具体例はどこから」→2段落や10段落が「中」に入るか検討。
「初め」「中」「終わり」にはなじみがあるが、
「序論(=初め)」「本論(=中)」「結論(=終わり)」
という言葉も同時に使うようにしていた。
5時間目
- 5分音読練習
- 30分「中」を分ける / 「原因と結果」の関係を考える
◎「『中』を二つに分けるならどこ?」
・具体例で、「結果」とその「原因」の説明を見つける
- 10分文章の構成を完成させる
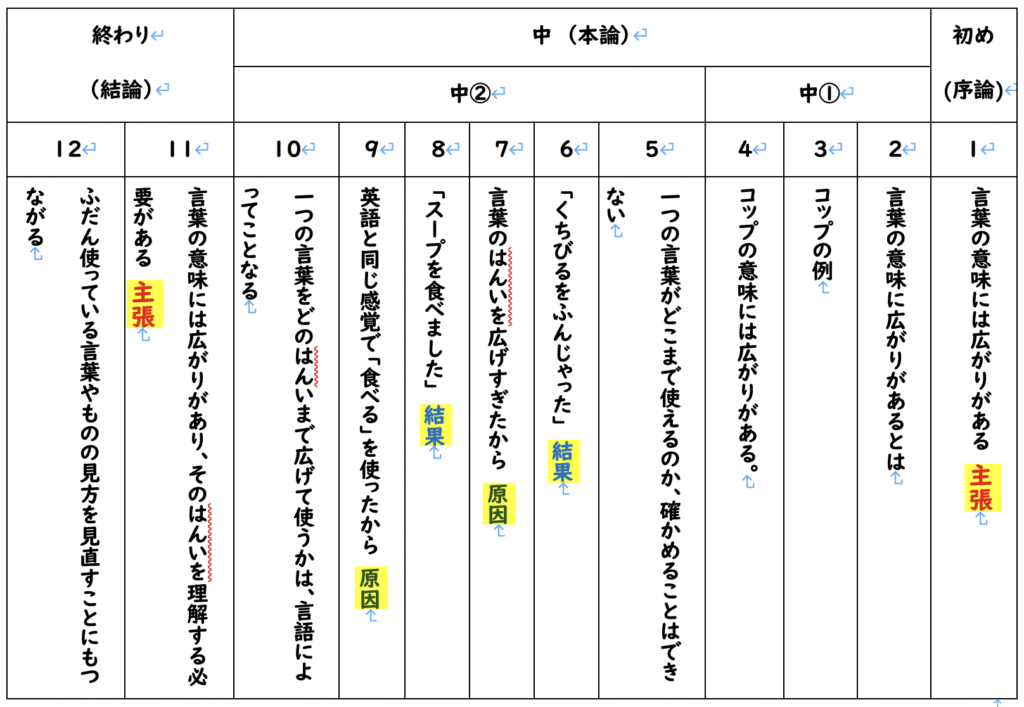
「中」を分ける
「中」が長いので、もっと分けることができないか。
本論も、内容によって、いくつかに分けられることに気づかせる。
6時間目
- 5分前時の振り返り
原因と結果の関係
- 30分原因と結果を使って、自分の考えを伝える
(情報:「関係をとらえよう 原因と結果」)
・何が原因で、何が結果とされているか考える(教科書から)
◎原因と結果を意識して、身の回りの出来事を使って、文を作ろう
- 5分振り返り
「原因と結果」の文作り
・2文か3文にする。(条件をつけると思考・比較しやすい)
・できたら、どこが「原因」・「結果」なのか、ラインを引かせる。(自覚させるため)
・新聞で「原因と結果」の文章を探してみるなど、他の文章に目を向ける活動に発展させる。
7時間目
- 5分音読練習
- 30分要旨をまとめる
150字以内で要旨をまとめる
- 5分振り返り
どんな文章の構造を学習したか、どんな場面で活かせそうか話題にする
要旨を捉える
「初め」と「終わり」に重なる筆者の主張を用いて、要旨をまとめる。
例:「言葉の意味には広がりがあり、「言葉の意味が分かる」とはおく深いことだ。言葉を適切に使うためには、言葉のはんいを理解する必要がある。言葉を学ぶときには、意味を「面」として理解することが大切であり、ふだん使っている言葉や、自然だと思っているものの見方が、決して当たり前ではないことにも気づかせてくれる。」(149字)
要旨:その文章や発言が最も言いたいこと。作者の言いたいことを「掴む」。核心
要約:文章全体を短くまとめ直したもの。全体を「縮める」(要点をつなげていくイメージ)
要点:文章で重要な点。複数あることが多い。細かい重要事項を「抜き出す」(キーワード)
要約は、それぞれが重要だと思ったワードをつなげている分、主観が入り、まとめ方に少し違いが出てくる。一方、要旨は、筆者の最も伝えたいことを捉え、短い文でまとめているため、全員が同様のまとめになる。
前の時間→「見立てる」
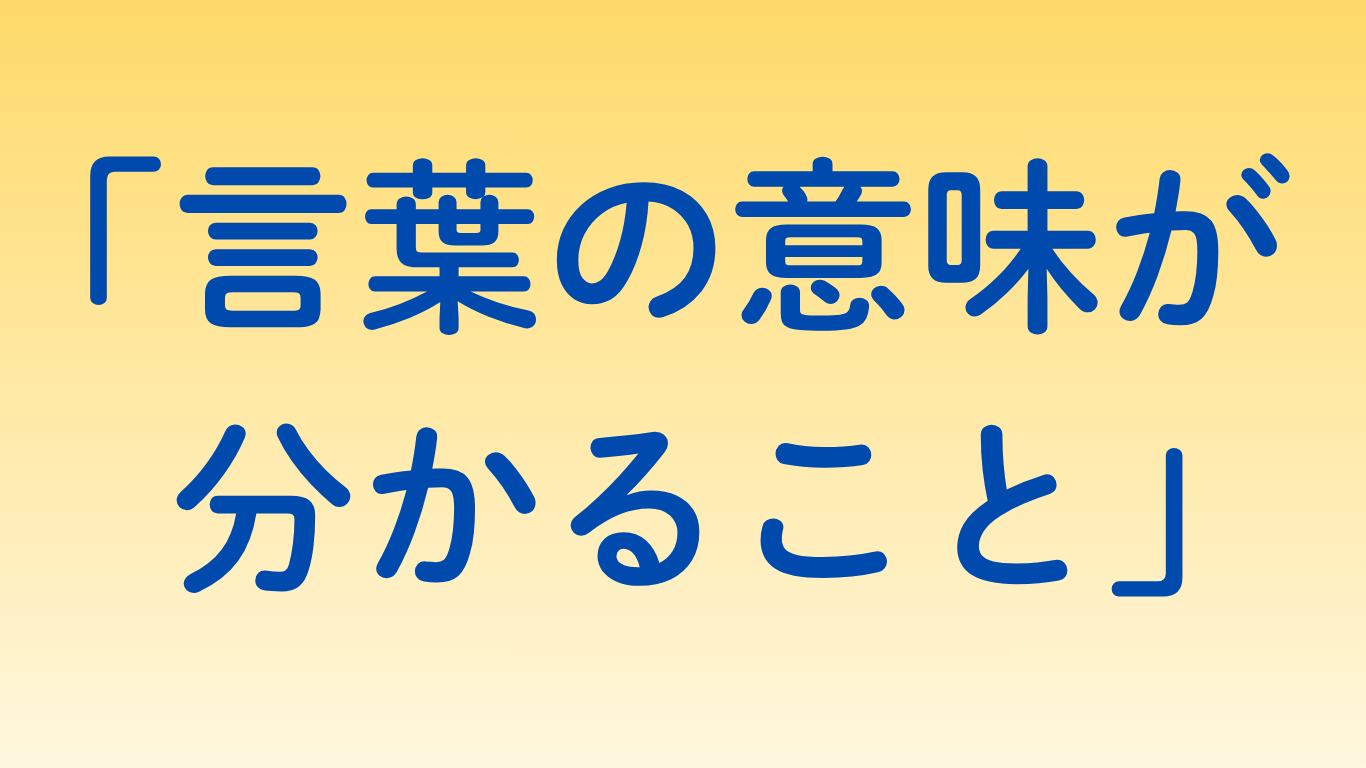
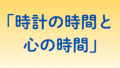
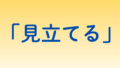
コメント